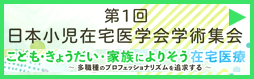Most Impressive Case Report 2016.03 研修医A
Most Impressive Case Report 2016.03 研修医A
【患者さん】 67歳 女性
【診断】
#1 統合失調症 #2 認知症 #3 慢性呼吸不全 #4高脂血症 #5 肺梗塞後 #6 肺高血圧症
【往診までの経過】
祖母、実母が統合失調症。14歳時に両親離婚。15歳時に今の義母と再婚。15歳頃から幻聴あり。
1968年、18歳時に統合失調症の診断。20年以上の精神科入院を経て、以後は内服治療を続けていた。
2011年頃まで一人で精神科受診や外出できていたが、転倒エピソード契機に恐怖から一人での外出ができなくなった。また若年性認知症の進行もありADLが徐々に低下。2011年3月民生委員の紹介で訪問診療利用開始となった。
【生活歴】
<ADL>トイレ歩行可 <排泄> 自力で可
<食事> 経口摂取(全介助)
【日常生活自立度】 寝たきり度 B2 認知症の状況 Ⅱb
【家族背景】 母(再婚後)
【医療デバイス】 在宅酸素(3~5L)
【医療資源】 訪問診療
【現在処方】
ロゼレム、ニュープレチル、ヒベルナ散、アタラックスP、リスパダール、レボトミン、メバロチン、テグレトール、サイレース、アモバン、センノシド、ロラメット、グッドミン、ワーファリン、SPトローチ、マグラックス、ピコスルファートNa
【往診導入後経過】
2011年3月民生委員の紹介で訪問診療利用開始。
週1回通所サービス利用していた。
労作時の呼吸苦、嚥下困難がもともとあって食事中は母が見守っていたが、誤嚥性肺炎で入院エピソード数回あり。
2011.12月急性の呼吸困難あり。病院受診。下肢の血栓が飛んだことによる肺塞栓症の診断。呼吸苦緩和の目的でHOT導入。
以降は呼吸の苦しさを理由に外出やデイサービスの利用をしなくなり、家から全く出かけない生活になった。
2013.4月母のレスパイトと緊急時の保険のためにSS利用してみたが、SS中に気道感染で救急搬送となり、SS利用に消極的となる。母は施設より病院の方が安心と考えるようになった。
2015.5月母の兄の介護と葬儀のためにレスパイト入院。
【今後の介護について】
介護のキーパーソンである母は生来健康な85歳、最近めまいを起こし、健康に不安を覚えた。今後何かあった際かかりつけ医を持っていない。また母の緊急時、娘さんの介護をどうしたらよいかという問題。今後は地域包括支援センターとSW、CMと共に具体的な医療資源の介入について検討する。
【スケジュール】
定期往診週2回
【老老介護の現状、問題点、対策】
現在の65歳以上の高齢人口は25.1%(H25年10月、前年24.1%)であり2007年から超高齢社会(高齢化率21%以上)の域に達している。厚生労働省が発表する「国民生活基礎調査(平成25年)」では、自宅で暮らす要介護者を主に介護する介護者が65歳以上の世帯の割合は51.2%となっている。さらに、介護者と要介護者が75歳以上という超老老介護の世帯の割合も、29%と、在宅介護者の半数以上が老老介護と直面している。
核家族化が進んでいるため老老介護の世帯が増えて行くのは当然だが、長寿国であるために老老介護は高齢の夫婦のみで構成される高齢者世帯だけでなく、2世代同居をしている世帯でも見られる事例である。
高齢化に伴い、日本では認知症患者数も増えており、要介護申請を行っている認知症患者は平成22年には65歳以上高齢者のうち約9.5%を占める280万人と報告され、2025年には470万人になると予想されている。また、要介護認定を申請していない認知症予備軍はおよそ800万人以上と言われており、介護が必要になった主な原因として認知症は第2位となっている。
65歳以上の高齢者の実に10人に1人が要介護認定を申請している認知症患者であるという実態は、在宅介護を行う介護者も認知症であることが珍しくないことを示している。老老介護の状態であるうえに、介護者と要介護者の両方が認知症であるという認認介護というケースも増加している。
根本的に老老介護を解決するためには、施設入居か核家族化の解消が必要であるが、その前段階としてまず在宅サービスの利用で介護の負担軽減を図ることができる。デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイサービスなど、組み合わせ次第で介護者の負担は大きく軽減できる。
しかし、老老介護の問題点として情報収集力が弱いということも挙げられる。また都市部などでは孤立した環境で、地域とのかかわりが薄く、相談相手がいないといったケースも多いため、自治体が主体となり高齢者にも伝わりやすいメディアを活用し、地域全体で情報を提供することが大切と考える。また町内会、自治会といったより地域性の強い団体に属し、近隣住民とのつながりを持つことも介護者の身体的、精神的負担軽減につながると考えられる。
【感想】
今回のケースは67歳の娘が統合失調症、肺梗塞後でHOT導入されており、ADLはトイレの移乗程度の患者。生来健康であった85歳の母が介護のキーパーソンであったが、年齢に伴い、自身の健康に不安を抱くようになった。典型的ではないが老老介護がかかえる問題を目の当たりにした。根本的には核家族化の解決であろうが、同時に訪問診療、訪問介護の普及が必要不可欠であると改めて感じた。また需要過多の医療資源を効率よく生かすためには患者さん本人、家族の多種多様な社会的背景をしっかりと把握することがスタートラインであり、こういったことは日々の病院での診療ではほとんど意識したことはなかったためとてもよい経験となった。在宅診療は患者さんを中心とし、家族、往診の医師、看護師、ケアマネージャー、ソーシャル・ワーカー、ヘルパー、緊急時対応できる病院等、あらゆる医療資源を活用する事で成り立つチーム医療であり、そのどれかが欠けると不安要素を抱えた脆弱な医療となる。高齢社会が加速している今の日本で在宅療養の占める割合が増えるにつれ、適切なサービスを適切な患者に行き渡らせるために、多職種の役割を把握することが大切であると感じ、また中核病院で働きながらも訪問診療、地域医療の動向に注目していこうと思った。