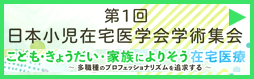Most Impressive Case Report 2016.04 研修医B
Most Impressive Case Report 2016.04 研修医B
【患者さん】76歳 男性 要介護3
【診断】#1 舌癌(T2M2cN0 stageⅣA) #2 胸膜播種 #3 肺転移 #4HBVキャリア
【往診までの経過】
2012/12頃、舌の違和感に気付きA病院口腔外科を受診した。生検を行い舌癌、両側頸部リンパ節転移の診断となった。2013/1より入院し、化学療法・放射線療法、陽子線治療などを行い一度は癌の形は消失し2013/3退院となりB病院歯科口腔外科で定期的に診察を受けることとなった。2014/1、CTにて右肺に小結節を認め、同年12月に増大、右胸水貯留も認めた。肺転移が疑われ、C病院紹介となり、1月より化学療法開始された。しかし、肺転移巣は増大し、徐々に化学療法の効果不十分となり、2015/11に治療困難と判断された。その後は緩和医療科受診となったが、徐々に通院も困難となりケアマネージャーからあおぞら診療所新松戸紹介され、2016/2より訪問診療導入開始となった。
【ADL】
<移動>室内歩行可 <排泄>自立 <食事>普通食 <清潔>自立(三日に一度)
【日常生活自立度】
寝たきり度 A2
【家族背景】
妻と2人暮らし 本人がキーパーソン
長女 東京在住 次女 千葉在住
【医療デバイス】
4/26時点
在宅酸素、尿道バルーン、点滴、PCA
【医療資源】
訪問診療、訪問看護、介護保険、ケアマネージャー
【退院時処方】
デカドロン、ランソプラゾール、ダラシン、アルダクトン、チラージン、バラクルード、カロナール、オキノーム
【往診導入後経過】
・2/23、初回往診。本人の希望もありデカドロン8mgから4mgに減量。
・3/24、疼痛のため睡眠が妨げられており、オキシコドン徐放剤5 ㎎開始。悪液質徐々に進行。
・3/28、温湿布で腰背部に低温火傷。
・4/1、排尿に時間がかかるようになり尿道バルーン提案するも、トイレまでの移動も楽しみの一つと、このときは拒否。
・4/5、便秘のためマグラックス処方。
・4/12、体動時呼吸苦あり、在宅酸素導入。
・4/14、排尿困難が持続し、移動も困難となりバルーン挿入となった。ルート確保しデカドロン点滴。薬の管理も厳しくなってきている。呼吸苦にオプソ追加となった。
・4/17、やや改善したためか、ご本人から点滴継続希望あり。ADLはベッド上となり、眠っていることが多くなってきた。
・4/21、妻も定時薬の管理はできている。レスキューに関しては本人の訴えがないと判断できないと。
・4/26、傾眠傾向強くほぼ内服ができなくなりPCA導入
【スケジュール】
2/23 初診
定期往診 12回、臨時往診 1回
電話 12回 、訪問看護 6 回
【癌末の方の在宅診療の問題点】
1)意志の尊重と治療のジレンマ
この患者様の場合、疼痛のコントロールのためのレスキューとしてオキノームが選択されていたが、できる限り服用したくないような様が見受けられた。
→ 本人の希望に沿うことが何よりであるが、どのような形が最も納得できるのかということを、具体的に把握する。どのような考えが服薬を妨げているのか、そこに誤解がないかどうか確認する。
また、バルーン挿入に関しても一度は拒否されており、できる限りのことを自分自身でしたいという意志が表示されている。
→ 治療の選択肢を提示し、利点・欠点を十分説明したうえで、患者様の選択の自由を奪わない。治療として正しいことも本人にとっては不快であるかもしれない。
2)キーパーソン
本人がキーパーソンとなっていたケースである。妻は口出ししづらい様子で、そのまま服薬管理や治療方針の決定からフェードアウトしていっていた。そのため本人の病態・状況について十分な理解ができておらず、「大丈夫なのか」と毎回医師に尋ねるなど、不安を見せていた。薬の管理や治療の選択を行うのが本人だけである場合、本人が判断できなくなった最終末期に決断ができなくなってしまう。
→ 癌末の方の在宅診療を行っていくうえで家族の協力は重要である。本人の意思を尊重しつつも、服薬管理や治療の説明を家族含めて行い、いい意味で家族を巻き込んでいく。また、本人の判断が厳しくなってきたとき、患者様本人の意思をくみ取ることができているようになっていなければならず、本人がキーパーソンであっても、家族が診療から外れるようなことは避けなければならない。
3)自宅で看取るという自覚
最期を自宅で迎えたいとはっきりとした意志の基、在宅診療に入る方と比べ、通院困難を理由に訪問診療が始まった家庭ではお看取りの自覚や覚悟が薄い。
→ 家族側が最後を迎える準備をしっかりできていなければならない。医療機関の中でも情報共有を行い、地域全体で一人の患者様とその家族を支えていく。
ご本人の弱っていく姿をみて、妻も診療に積極性がでてきたように感じられる。
【感想】
往診に同行してとても印象に残ったのは、患者様を支える家族の表情が生き生きしていることだった。どのようなケアが必要で、どのように治療していくのかということに対して非常に熱心である様がうかがわれた。病院では大掛かりな検査や治療ばかりであるためか、深い理解を得ないまま患者様ご家族は医療者に検査や治療をする判断を委ねることが多いように感じられたが、それと対照的であった。治療は患者様本人やご家族の協力を得て初めて成功するのだということを実際に体現されていた。さらに治療に携わっているというやりがいが、患者様を支えるご家族を明るくさせているようにも思えた。今までは在宅診療の良さは自宅で看取ることができるという点しか頭になかったが、このような面でも在宅診療の良さが発揮されているのだと感じた。もちろん良い面ばかりではなく、自分の生活にプラスして介護をするということは家族にとって負担でもあるため、それをどのように和らげていくかが在宅診療の難しさでもある。ひとつの家庭に多くの機関が関わり、情報を共有することが重要なのだと伝わってきた。この一カ月、地域医療研修では、『共有』が大事なキーワードであった。