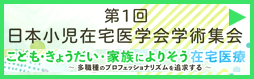Most Impressive Case Report 2020.10 研修医A
Most Impressive Case Report 2020.10 研修医A
【症例】 8歳 男性
【診断】Diffuse Intrinsic Pontine Glioma(DIPG)
【既往歴】気管支喘息
【周産期歴】39週4日 3176g 正常分娩
【発達歴】異常なし
【現病歴】
生来健康
X年12月(7歳11か月) 内斜視出現
X+1年4月 サッカーがうまくできなくなった。
5月 右顔面神経麻痺が出現。
5月14日 A病院受診。左外転神経麻痺、右中枢性顔面神経麻痺、右優位の小脳症状、両側下肢の腱反射亢進あり。MRIで橋を中心とした粗大な占拠性病変あり。
画像的にDiffuse Intrinsic Pontine Glioma(DIPG)と診断、生検は希望されず、
通院での治療を希望
5月18日 デカドロン2㎎/日内服を開始
5月26日~7月6日 原発巣に対して、56Gy/30Frの放射線治療を実施。
デカドロンは漸減中止。7月20日に終了。
A病院で早期の在宅医療導入提案され、両親が希望。
8月17日 当院の在宅医療導入。
【内服薬】デカドロン 2㎎ 2T、モンテルカスト1錠1×、アレロック 1錠1×
【栄養】経口摂取可能 みなと同じものを食べている。
【訪問診療導入後経過】
関係性構築のために早期から在宅医療を導入。
両親の願いは親にも言えないようなことを話せる相手になること。
8月17日 初回往診。DEX中止後体調不良。少量コートリル内服中。
8月31日 往診②山梨に旅行、サッカーもできるようになり安定している。
9月23日 往診③サッカーの試合でもしっかり走れるほどになった。
9月29日 食欲なし、頭痛あり
10月2日 サッカー中、右足の運びがおかしい、言葉がうまく話せない。
10月3日 ブロッコリーを喉につまらせた。頭痛ひどく、カロナール効果なし。
10月4日 朝から頭痛あり、サッカー休む。
10月5日 往診④神経学的所見悪化疑い、A病院受診指示。
10月6日 A病院受診 単純CT施行、デカドロン2㎎内服再開
10月13日 A病院でMRI施行。右小脳脚を圧排する嚢胞状構造の増大あるが腫瘍自体の増大はなし。
10月19日 往診⑤デカドロン内服後、動揺歩行は改善状態を確認。頭痛なし。
自傷行為は、デカドロン+少量コートリル(5-3-2㎎)でやや改善。
今後の予定)11月27日にA病院で、MRI再評価。
【考察】
~DIPGについて~「DIPGは、Diffuse midline glioma の一つ」
好発年齢:5歳から9歳
分類:ヒストン修飾因子である、H3.1 H3.3が変異したH3-K27Mtype、悪性型のMYCN遺伝子増幅をもつMYCNtype 中間型のsilent typeに分類できる。
組織:繊維性星細胞腫や膠芽腫像まで様々な像を呈する。
(病理所見で診断はしない。組織学的にGradeが低くてもH3K27M変異があればgradeⅣ)
診断:画像で診断する。 頭部MRI 橋の腫大、境界不明瞭な腫瘤、T2WIでhigh 、T1WIでlowが典型的
症状:脳神経症状として眼球運動障害、顔面麻痺 小脳症状として失調性歩行 錐体路徴候として運動麻痺
治療:放射線治療がfirst choice 1.8~2.0Gy/日を連日 計54Gy前後で治療
有効とされる抗がん剤治療はなし。
予後:放射線治療単独の場合、生命予後は1年以内。
3歳未満の若年、17歳以上の予後は比較的良好。→通常のDIPGとはgeneticに発生原因が異なると考えられる。
~本症例の医学的考察~
・頭部MRIで、橋右側中心に腫瘍あり、橋右背側に突出する嚢胞性病変あり、右小脳脚を圧排
本児の症状は右顔面神経麻痺、右外転神経麻痺、小脳症状、錐体路徴候がみられており、画像所見に合致。
・10月に神経学的増悪があったのは、偽性進行ではないか。
・予後は、本児の場合2年未満である可能性が高い。(診断時の脳神経麻痺の存在、リング状造影、壊死、および橋外への進展が挙げられる。これらの特徴を有する患児の2年生存率は10%未満)
【本症例を通して】
緩和ケアは、生命の危険のある疾患を持つ患者及びその家族に対して、その診断から生命の終わりや遺族ケアに至るまで行われる、痛みをはじめとする諸症状の緩和と霊的、心理的なサポートのことをさす。
本症例では早期在宅導入をしたことで、「言いたいことが言える」関係を構築でき、本人・家族の精神的安定だけでなく、家族の心理的な準備が整っていくと考える。また、子供を取り巻く環境は、成人の場合と比べて多様である。患児には小学生の兄がいる。両親のケアは当然として、親の関心が患児に集中する環境で、深く傷ついていることも多い同胞のケアも非常に重要なテーマになると考えられる。
Not doing but being 何かをすることではなく、傍にいること。
苦しみを分かち合うこと、ただ話を聞き、できるだけ一緒に笑い、家族と子供が楽になるためにできることを考え続けること、一緒に揺れることを積み重ねていくことが傍にいること。
しかしそのなかで、本人のためにできることをみつけて、患児を笑顔にするため、ウクレレ演奏や歌を歌うなど真摯に向き合う先生の姿をみて非常に感銘を受けた。
それをみていると、なにかが出来ることではなく、そこに今在ること、あなたの存在が大切であると、子供に伝えているように感じた。先生の暖かい音楽で、家族の雰囲気も和らいでいた。将来児童精神科医になることを志しているが、この考えを大事にしたいと強く思った。
また、病院でみる姿だけでなく、家や学校での本人の様子をみることで、その子の「生活」がわかる。とくに、児童精神の領域では、実際にその子の生活の実態を知ることが診療のうえで一番大切といっても過言ではない。将来的に、児童精神科医の立場で往診もしていければと強く思った。
~参考文献~
1)日本小児血液・がん学会編集「小児がんの在宅緩和ケア」前田浩利,戸谷剛 著
2)Neuro-Oncologyの進歩Vol23-1「小児脳幹部グリオーマの歴史と展望」浅野研一郎著